|
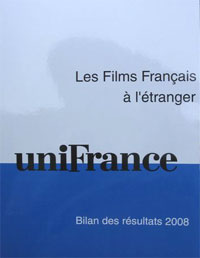 |
|
ユニフランス白書08
|
フランス映画の統計資料は毎年、カンヌ映画祭開催期間中にCNC(フランス国立映画センター)会長により発表される。その際、前年の統計をまとめた映画白書も配布される。160ページに及ぶ大部で、フランス映画の前年の記録が網羅され、映画関係者、研究者にとり貴重な資料である。そのうち、輸出の章では、フランス映画の海外市場での受け入れられ方が詳述され、日本のフランス映画状況についても知ることが出来る。
フランス映画の海外プロモーションを専門に行うのが、CNCの直属組織、ユニフランス・フィルム(以下ユニフランス)である。1949年に設立され、プロデューサーを中心とし650人の会員を擁し、フランス映画の海外プロモーションを手懸け、年間予算は約10億円である。会長は、プロデューサーが務めることになっており、前任者のマルガレート・メネゴズの任期満了に伴い、同じく、プロデューサーのアントワンヌ・ドゥ・クレルモン=トネールが新会長に選出された。パリの本部職員は30人、海外はニューヨーク、東京、北京に事務所を構え、ニューヨーク、インド、日本、中国、ハンガリー、ブラジル、ロシアでフランス映画祭を開催している。日本では既に17年前より、フランス映画祭が催され、現在も続いている。
「フランス映画祭 東京」は、アジア市場の拠点作りの意味合いがあり、ユニフランス
も力を入れているフェスティヴァルである。他に、ユニフランスが一番力を入れる催しに、毎年一月にパリで開く「ランデヴー」がある。主としてアメリカ、ヨーロッパの有力バイヤーを招いての、フランス映画見本市である。
ユニフランスのデータブック「ユニフランス白書」によると、
2008年の海外輸出は過去最高であった。
具体的数字は下記に記す:
・ 海外市場での入場者数 8450万人
・ 海外市場での興行収入 4億2100万ユーロ (547億3千万円)
・ 公開国数 64ヶ国
・ 公開本数 401本
・ 百万人以上の入場者数国 16ヶ国(アメリカ、ロシア、ドイツなど)
・ 百万人以上の入場作品 15本
ベスト3−「バビロンAD」,「アステリックス、オリンピックへ」、「Taken」など
フランス映画の海外戦略にとり、最大のネックはフランス語自身である。現代世界はアメリカ中心であり英語がほぼ世界を席巻し、フランスも英語の脅威にさらされている。
例えば、フランスの隣国、ドイツやスペインでもフランス語より英語の方が通りが良い。世界的に見てフランス語はナショナルな言語である。しかし、映画に関しては、元祖を自認し、アメリカと並ぶ映画大国である。
このフランス、フランス語作品の海外浸透にはひどく手を焼き、今、なお苦戦を強いられている。一例として、アメリカの映画市場を挙げてみる。同国の映画人口は13.6億人と巨大な動員数を誇り、自国映画の市場占有率は95%と外国映画には僅か5%と、単一マーケットの様相を呈している。
この5%の中でフランス映画の占める割合は1.3%、数値的には微少だが、大健闘ともいえる。残りの3.7%に世界各国映画がひしめき合い、日本映画はその極小スペースの中に位置する。アメリカ市場のフランス映画の入場者は1782万人、興行収入は8941万ユーロ(約116億円)。公開本数は41本となっている。如何に、外国映画にとり、アメリカ市場が厳しいか、95%の自国作品占有率を見れば良くわかる。
米国市場の厳しさを打破すべきフランスは、自国語ではなく英語版製作という手法を編み出した。アメリカの外国映画は殆どが吹替えで、我が国のように字幕ではない。ここにアメリカ国民の自国語への強い執着が見られる。因みに、フランスでの英語圏作品上映は字幕である。勿論、カンヌ映画祭の英語圏作品も字幕上映である。
英語版とは、吹替えでなく、撮影時からの英語撮影である。フランス映画はフランス語吹替版と英語撮影版の二種となる。
海外公開された英語撮影版のベスト3は「バビロンAD」(マチュー・カソヴィッツ監督、アクション)、「Taken」(ピエール・モレル監督、スリラー)、「トランスポーター3」(オリヴィエ・メガトン監督、アクション)、吹替版のベスト3は「アステリックス、オリンピックへ」(トーマス・ラングマン、フレデリック・フォレスティエ監督、コメディ)、「シュティスへようこそ」(ダニー・ブーン監督、コメディ)、「潜水服は蝶の夢を見る」(ジュリアン・シュナーベル監督、ドラマ)
英語撮影版フランス映画は、数字的に海外で好成績を収めている。
その代表が「バビロンAD」。
|
|
|
入場者数
|
興行収入
|
公開本数
|
| 1. |
アメリカ
|
1782万人
|
8941万ユーロ(116億円)
|
41
|
| 2. |
ロシア
|
738万人
|
3417万ユーロ(44.4億円)
|
51
|
| 3. |
ドイツ
|
579万人
|
3400万ユーロ(44.2億円)
|
48
|
| 9. |
韓国
|
313万人
|
1278万ユーロ(16.6億円)
|
25
|
| 16. |
中国
|
101万人
|
275万ユーロ (3.6億円)
|
3
|
| 20. |
日本
|
82万人
|
796万ユーロ (10.3億円)
|
40
|
この数字から日本を含むアジア各国の苦戦振りが際立つ。中国は入場者数が前年比の25%減であるが、政府の本数制限政策により公開本数が極端に少ない。通常は5本公開されるフランス映画は、2008年は3本と後退した。しかし、将来、緩和の可能性があり、フランスにとり目が離せない市場である。
お隣の韓国、日本、中国と比べ健闘の部類に入る。それはスリラーの「Taken」の好成績によるもの、240万人動員の大ヒットである。しかし、他の国々で好調の「バビロンAD」と「法外な価格」がそれぞれ22万7千人、13万人と惨敗し、全体の数字の押し上げはならなかった。
日本では芸術扱いで客離れ
我が国のフランス映画への関心は決して低くない。しかし、それが観客動員へとつながっていないところが問題なのだ。
60年代までは、フランスを中心とするヨーロッパ映画は確固たる地位を確立していた。しかし、70年代からのアメリカ映画攻勢と観客の嗜好変化より、フランス映画輸入は大幅に減少した。そして80年代以降、本数は多いが、殆んどがアート系館興行のため、収入が減少した。一番大きな要因は日本人のアメリカ指向と思われる。フランス映画はアート系館上映にあぐらをかき、より上を目指さなくなったことも考えられる。更に、フランス映画は、大学の仏語教官を中心とするグループにより、小難しい作品が芸術的とする風潮が定着したのも一因。その一例が、ヌーヴェル・ヴァーグ、カイエ・ドゥ・シネマ信奉者の存在であり、フランス映画は難しく、退屈とし観客離れが起きた。
昨今の不景気で、小規模なアート系館や配給会社の不振という事態が起り、状況は好転の兆しが見えない。
ここ数年の日本におけるフランス映画状況を見てみよう:
|
年
|
上映本数
|
入場者数
|
|
2003
|
43本
|
420万人
|
|
2004
|
44本
|
189万人
|
|
2005
|
34本
|
172万人
|
|
2006
|
40本
|
135万人
|
|
2007
|
42本
|
298万人
|
|
2008
|
40本
|
82万人
|
以上のように入場者数は前年比75.7%減、興行収入は69・4%減と並の減少ではない。この減少について、メネゴズ前会長は、フランス映画祭を横浜から東京へ移し、ビジネス中心へと方向転換を行い、フランス映画のシネコン上映で観客増を狙った。しかし、現在までその効果は見てとれない。
今年のカンヌ映画祭時に、ユニフランスの幹部に日本におけるフランス映画人口の減少について話を聴いた。しかし、2008年のフランス映画輸出の記録更新へ目が行き、日本市場に対する具体的施策については明確な方向性を打ち出した意見は聴かれなかった。
多分、ユニフランスとしても解決策を探しあぐねているのが現状ではなかろうか。将来的に、日本市場に見切りをつけ、中国、韓国へと軸足を動かす選択肢も可能なのだ。「フランス映画祭 東京」も消滅するかも知れない。日本に於けるフランス映画人口増の具体的な方策を立てる時期が来ている。
(文中敬称略)
《了》
2009年7月6日号 映像新聞掲載
中川洋吉・映画評論家
|
